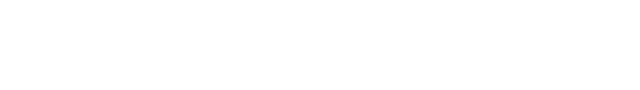院長が大学で留年を覚悟した瞬間を振り返るーその 1
医学教育は医療技術や知識とともに日々進歩しており、以下のようなことが当たり前になっています。
・入学直後の 1 年生からすぐに病院の実習を経験して患者さんと話をさせてもらい、医師になるという気持ちを高める
・3〜4 年生の学生がそれぞれ研究室に所属し一流の研究者から基礎医学における実験の実際を体験する
・英語ネイティブで国際的にも一流とされる総合診療医による少人数制での確定診断にいたる臨床現場さながらのワークショップ
・海外一流大学への短期臨床/基礎留学
などなど。これらはすべて母校である東京科学大学の医学生が(セレクションがあるものももちろんありますが)履修できる素晴らしいカリキュラムの一部です。
ひるがえって院長が大学に入学したほぼ 30 年前の 1995 年当時、概して医学部のカリキュラムは
1-2 年: 教養課程として生物ならまだしも、大学受験で散々勉強してもう「解放される!」と思っていた物理・化学や体育を履修
3-4 年:基礎・臨床医学の講義をひたすら聴く。
5-6 年の前半:臨床実習と称して大学病院内や関連病院と呼ばれる大学と関連の深い病院で「お客様」みたいに若手の先生にくっついて見学をする
6 年の後半:卒業試験と国家試験のためにひたすら勉強勉強
・・・とまあこんな感じでした。
かなりキツキツに講義が組まれており、まともに勉強するとその知識量は膨大(当時より 30 年近く医療が進歩しているので現在の医学生はもっと大変でしょう)で、かなりの負担でした。
そうなると留年せずに進級するには「要領の良さ」が重要になってきます。
この辺の事情については明日に続きます。

イラストは Chat GPT が生成した "日本の医学生たち" です。ちなみに院長はこんなにイケメンで透き通るような肌は持っていません・・・。