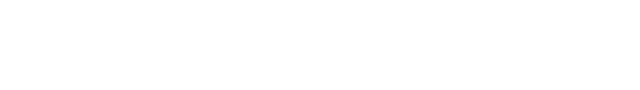院長の書評その 6:南 杏子 先生『サイレント・ブレス』ー 終末期・在宅医療は医療の「影」ではない
本作品は主人公の 10 年目医師である水戸倫子が、新宿の高度医療機関である大学病院から在宅医療専門施設である「むさし訪問クリニック」への異動を命じられるところから始まります。
一般的に言って、医療の「光」すなわち派手できらびやかで世間の注目を集めやすいのはロボットによる超微細手術・ゲノム解析に基づくテーラーメイド医療・AI による診断補助、などのいわゆる「最先端」の技術でしょう。
それらに対して、進行したがん症例、効果的な治療がない進行性の神経変性疾患(ホーキング博士が罹った筋萎縮性側索硬化症(ALS)など)、介護施設における診療などはどちらかというとマスコミの扱いは「影」の印象があります。
しかしながら、われわれヒトの死亡率は何パーセントでしょうか。そう、100% です。ヒトはいつか必ず亡くなるのです。2022 年の日本における総死亡数は 156 万 8961 人であり、日本中で考えれば 1 分間に 3 人が亡くなっている計算になります。そう考えると超高齢社会を迎えたわが国において、在宅医療や終末期医療はもはや「影」ではなく、すべての人が「最期をどう迎えるか」考える必要があります。
水戸倫子医師は在宅医療施設に異動が決まり、医療の「影」の役割を担うことになってしまうと思ったのでしょう、当初は「左遷だ」と思いますが、結果としてクリニックに入職して終末期医療などの様々な現場を経験することで医師として精神的に大きく成長します。
これは、2004 年 12 月から 2023 年 3 月までのおよそ 18 年にわたって東京の大学病院と国内一流といってよいがんの専門病院に在籍し、その後昨年 4 月に(神奈川県の中心である横浜や川崎から遠く離れた)秦野市にうつって町医者をやっている院長にとって、極めて感情移入しやすいシチュエーションです。院長はこの転身を「左遷」とは考えたことは一度もありませんが、長らく行ってきた「最先端医療の提供者」とは大きく異なる「かかりつけ医」としての経験により、日々少しずつ成長している実感があります。当院に通ってきてくれる患者さんやスタッフ、家族のおかげです。
作者の南杏子先生は、院長が日頃お世話になっている東海大学医学部を 38 歳で卒業、子育てしながら研修医生活を乗り切り、病院勤務の傍らカルチャーセンターで小説教室に通って 55 歳で作家デビュー、という異色の経歴をもつ医師兼作家です。現在 47 歳、近い将来小説家デビューを狙っている院長にとって、素晴らしいお手本のような方です。
医師は様々な「生」を目の当たりにする一方、同時に多くの「死」も経験しなければならない職業です。近年「聖職者」とか「無償の愛」という言葉は死後になりつつあり、「医師も他の業種と同じ、単なるひとつの仕事」ととらえる考えが若い世代を中心に主流となってきました。ただしヒトの「生死」に関わる以上、少なからず宗教的というか観念的であることが求められる、やはり「特別な職業」ではないかと院長は考えています。
そのような思いを小説というフィクションとしてまとめられた南先生の本作品は、自分のみならず、多くの医師のかわりに実際の現場を代弁してくれているようでした。院長は読了時になんだか心の中にあるモヤモヤがスッキリした感じがしました。
興味ある方、是非手に取って読んでみてください。
作者の南杏子先生が「死は『負け』ではなく『ゴール』」とおっしゃっていましたが、われわれ医療者だけでなく、一般の方々にもこの意味を一度考えていただければと思います。そのきっかけに本作品は最適です。